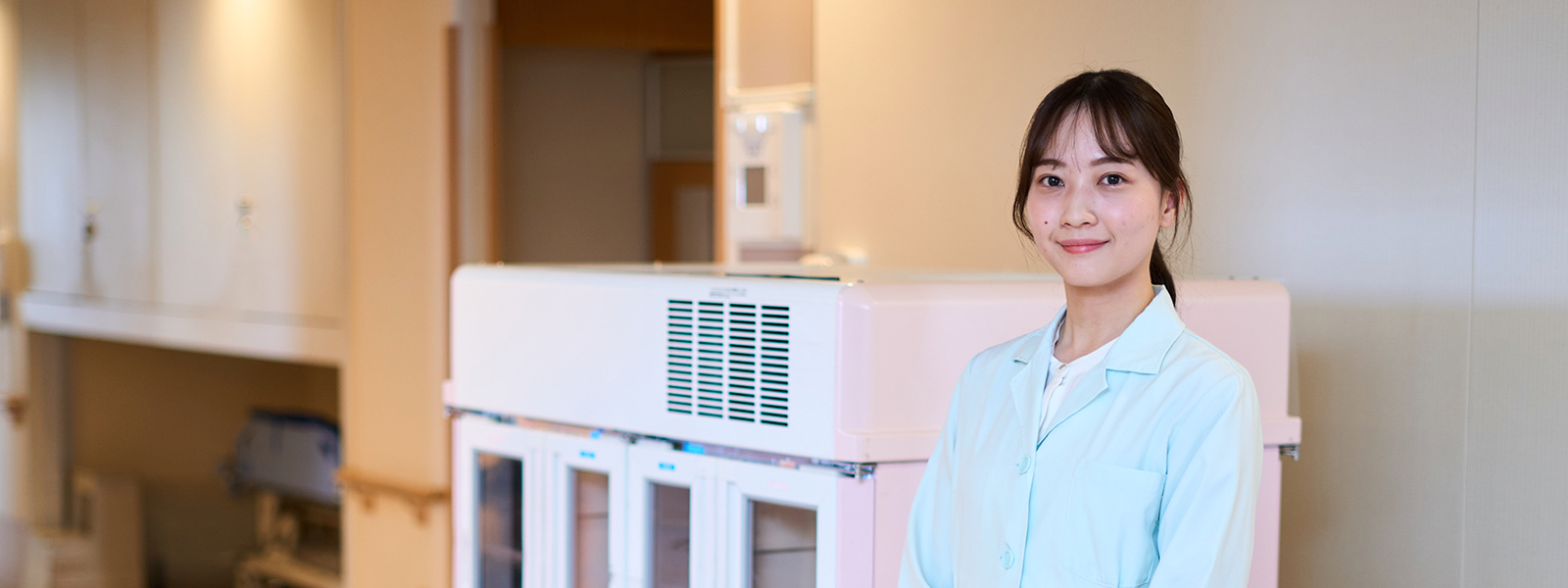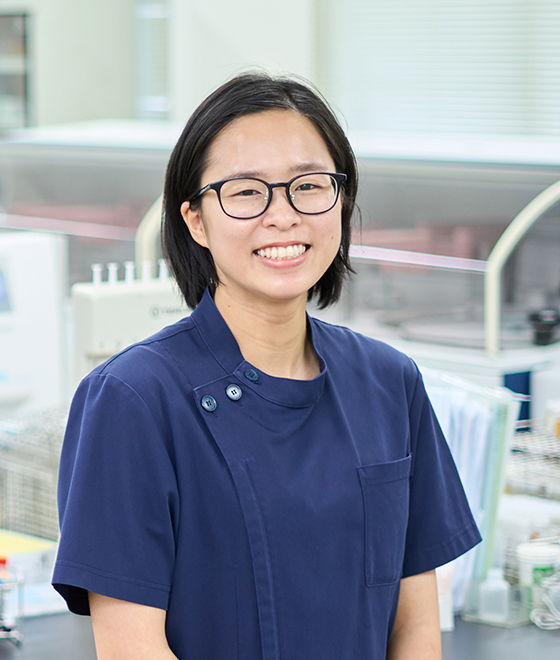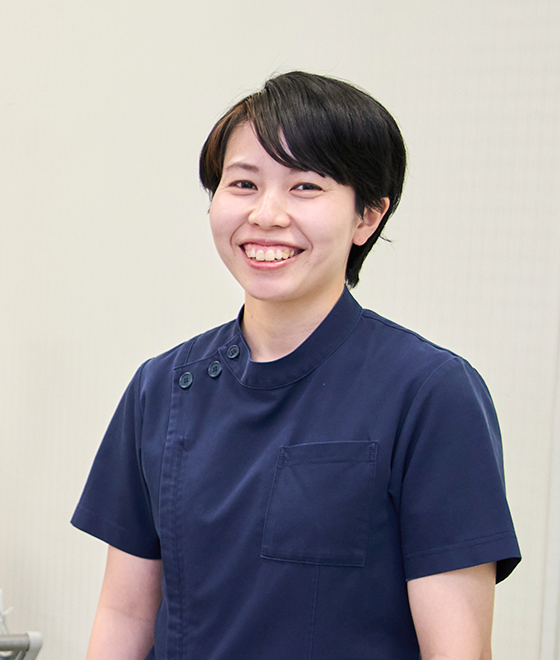少しずつできることが増えて、仕事の幅が広がっていく
病院の管理栄養士は狭き門。その分、すごくやりがいがあります。
入職して1年目はまず入院・外来患者さんの栄養指導を通して、いろいろな疾患のこと、それらの疾患と食事の関係について学びました。2年目からは担当病棟を持つようになり、先輩と一緒に動いて経験を積み、さらに「入院前支援」も担当するようになりました。入院予定の患者さんに対して栄養状態や食事内容の把握などを行い、入院中の栄養管理につなげていく窓口です。そして3年目で独り立ち。わたしの場合は同時にNST(栄養サポートチーム)にも関わらせていただくようになりました。だいどうクリニックでの外来栄養指導も行っています。
栄養のことは任せてください
入院中の食事は治療の一環。美味しく食事ができることは健康のバロメーターであり、食べられなければ病気の回復も難しくなります。食べることは生きることにつながります。もちろん、病気の影響でなかなか食べられない患者さんもいらっしゃいますので、プレッシャーを与えることなく、必要な栄養を摂っていただけるように工夫していきます。少しずつ食事の形態や内容を調整しながら、「食べられるようになった」「お腹がすくようになった」と言っていただけることが何よりも嬉しいです。
当院では、管理栄養士のこと頼りにし、意見を尊重してくれる医師や看護師が多く「ザ・チーム医療」だと感じます。特にNSTでは多職種が対等に意見を出し合い、他職種からの学びもたくさんあります。この環境にいると、自分ももっと役に立ちたいという気持ちが、自然と湧いてきます。
急性期だからこその、管理栄養士の役割
私が担当しているのは消化器外科の病棟。手術後の栄養管理、食事療法に関わることが多いです。「NST専門療法士」の資格も取得しましたので、さらに勉強して、周術期や救急の分野における専門性を高めていきたいと思っています。
急性期医療では「まずは治療が優先」という雰囲気に包まれることも多いのですが、栄養状態は回復のスピードや予後に大きく関わります。いかに早く栄養状態を立ち上げるかが非常に大切。水分量や栄養量の調整をし、誤嚥や下痢をしないで栄養を摂取できる状態を目指します。急性期病院の管理栄養士としてのバリューを、これからも追求していきたいと思っています。